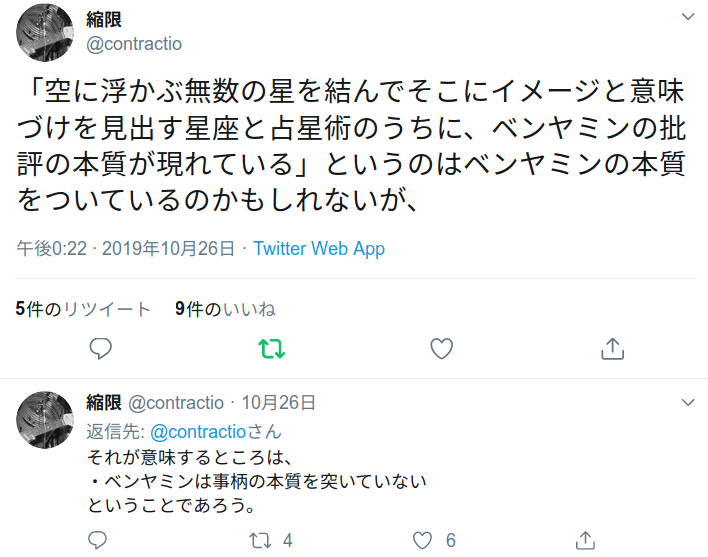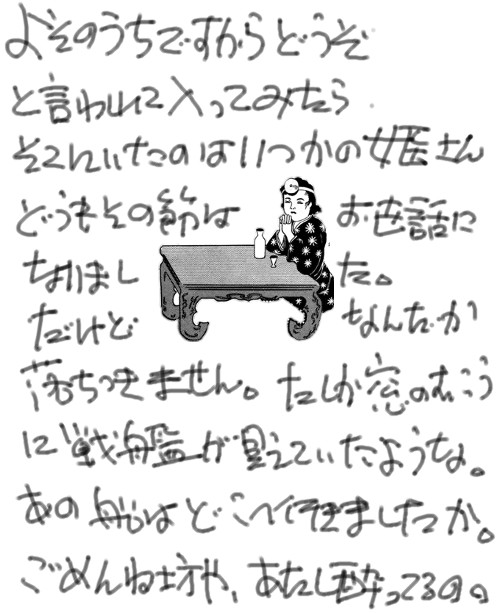2020.5.31 sun.
2020.5.30 sat.
2020.5.29 fri.
そのころ、ちゃんと「外に出ろ、自由でいろ」と言っていたのは僕の観測範囲では東浩紀と山形浩生くらいで、それもちょっと炎上気味だった。それからけっこうしてから外山恒一が「外出するだけで闘争になる」と、ユーモアあふれる発言をしてバズり、そこからなんとなく雰囲気が変わっていったという印象 ――樋口恭介『すべて名もなき未来』(晶文社)発売中 on Twitter
自分は怠惰というか保守的というか、寝てると起きたくないし、起きていると寝たくなくなる癖があって、大きな声じゃ言えないけど、今回も、せっかく世の中が動き出したってのに、今はむしろこのまま篭って自分の作品を作りを続けたくなっていて・・・もうちょい待ってってなっております。 ――大友良英 on Twitter
2020.5.28 thu.
ディスクからこんなのが出てきた。天球の外側のこと - Magazine Oi!
事実はみずからを語る、という言い慣わしがあります。もちろん、それは嘘です。事実というのは、歴史家が事実に呼びかけた時にだけ語るものなのです。いかなる事実に、また、いかなる順序、いかなる文脈で発言を許すかと決めるのは歴史家なのです。(…)シーザーがルビコンという小さな河を渡ったのが歴史上の事実であるというのは、歴史家が勝手に決定したことであって、これに反して、その以前にも以後にも何百万という人間がルビコンを渡ったのは一向に誰の関心も惹かないのです。(…)歴史家は必然的に選択的なものであります。歴史家の解釈から独立に客観的に存在する歴史的事実という堅い芯を信じるのは、前後顛倒の誤謬であります。しかし、この誤謬はなかなか除き去ることが出来ないものなのです。 ――E. H. カー『歴史とは何か』(清水幾太郎訳)
2020.5.27 wed.
#ポストコロナ
「僕は忘れたくない」と、この小説家は言う。でも、ほぼまちがいなく忘れるだろう。2年もたてば忘れる。ぼくは年寄りだから、エイズが流行ったときに、エイズ後の文明だのいう駄文がたくさん登場したのをよく覚えている。もはや人間同士の密な接触はなくなり、盆栽やお茶会みたいなゆるい枯れた人間関係しかなくなるだろう、なんてことがマジで言われていた。リーマンショック/金融危機で、資本主義は崩壊して新しい世界秩序が、なんて話は腐るほど聞かされた。そして、この日本では「ポスト福島」談義がみんな記憶にまだ残っているはずだ。 ――コロナを前にしたインテリの自己矛盾|新・山形月報!|山形浩生|cakes(ケイクス)
近くを流れる宮川の水には、いろいろな小動物たちが、何の拘束もなく、嬉々として日に当たっています。もちろんマスクもしていませんし、外出禁止も休業も要請されていません。えやみ ときのけ 老いの春 - 野口武彦 公式サイト
2020.5.25 mon.
直助は江戸深川万年町冬木店の医師の中島隆碩(赤穂浪士の脱盟者・小山田庄左衛門と同一人物説あり)を下男奉公していた。享保5年(1720年)12月、中島に薬種の横領を暴かれ、翌年正月15日宿請人に引き渡され詮議されるはずであったが、中島ら一家を斬殺し、金を奪って逃亡した。直助権兵衛 - Wikipedia
直助が「お前も余っ程強悪だなア」というのに対し、「おぬしが仕草を見習ったのよ」と伊右衛門がこたえるのは敵役の名人幸四郎に対する当て込みであろう。(…)大坂本の「いろは仮名」は、ここで伊右衛門が「首が飛んでも動いてみせるワ」ということになっている。(近ごろは東京でも、このセリフだけはいうようになった)これは敵役の性格描写として、巧妙なセリフだと思う。 ――戸板康二「東海道四谷怪談」解説(『名作歌舞伎全集』第九巻)
2020.5.24 sun.
2020.5.23 sat.
2020.5.22 fri.
2020.5.21 thu.
2020.5.20 wed.
彗星の本体 2 O、NH3 、CH4 などの氷が大部分3 で、相互に広い間隔をおいて存在し、彗星の核の95%は空所彗星の起源
2020.5.19 tue.
木下智恵 on Twitter
舞台――目の細い格子状の、鉄製の簀子舞台、背景も同様に、一面、格子状の壁によって覆われている。その向うに、時おり時代がかったイルミネーション、あるいはネオンサインによる「MAISON de PRINTEMPS 春心酒家」の逆さ文字が浮かぶことがある。他に、一切の装飾物なし。舞台は基本的には、終幕まで変化しない。 ――佐藤信『ブランキ殺し上海の春(上海版)』
2020.5.18 mon.
デカルトの心身二元論に関するエリザベート王女の問い。
2020.5.17 sun.
午前2時過ぎ、ハトの鳴き声で目をさます。サルバドール・ダリ伝記映画に「アメリカン・サイコ」メアリー・ハロン監督 : 映画ニュース - 映画.com
2020.5.16 sat.
夜の幽霊は死刑執行人の剣を見るとこわがると言われている。――もしも幽霊にカントの『純粋理性批判』をさし出したら、彼らはどんなにおどろくことであろう! この本はドイツで理神論の首をきった剣なのだ。 ――ハイネ『ドイツ宗教・哲学史考』(舟木重信訳、筑摩書房『世界文学体系78ハイネ』)
マクシミリアン・ロベスピエールをイマヌエル・カントと同列におくならば、それはロベスピエールに敬意を表しすぎることになる。サン・トノレ街の偉大な俗人マクシミリアン・ロベスピエールは、王制をうち倒すことになったときには、もちろん破壊的な憤怒の発作におそわれ、その次には国王の首をはねる癲癇になっておそろしくからだを痙攣させた。しかし話が至高の神についてのことになると、彼はすぐと癲癇の白い泡を口からふきとり、血みどろの両手を洗い、ぴかぴか光るボタンのついた青い色の晴れ着を着こみ、おまけに幅のひろい胸着に花束をさした。 ――同前
この二人は性来コーヒーや砂糖をはかり売りするように定められていた。ところが運命は彼らがほかのものをはかることを希望して、ロベスピエールの秤皿には国王をのせ、カントの秤皿には神をのせたのである。…… ――同前
2020.5.15 fri.
2020.5.14 thu.
2020.5.13 wed.
いつでもなお無害な観察者がいて、「直接的確実性」が存する、と信じられている。例えば、「われ思う」だの、或いは、ショーペンハウァーの迷信だった「われは欲する」だのがそれである。いわば、ここでは認識が純粋に、赤裸々にその対象を「物自体」として把握しえられ、主観の側からも対象の側からも偽造が生じないかのようである。しかし「直接的確実性」も「絶対的認識」や「物自体」も、同様にそれ自身のうちに《形容矛盾》を含んでいる。 ――ニーチェ『善悪の彼岸』16節(木場深定訳)
以前には、文法と文法上の主語とが信じられたと同じく、「霊魂」というものが信じられていた。「われ」は制約であり、「思う」は述語であり、制約されたものである、と言われた。――思うことは一つの活動であり、それには原因としての一つの主語が考えられなければならない 。さて、驚くべき執拗さと狡智とをもって、この網から抜け出ることができないかが試みられた。――もしかすると、その逆が真なのではないか。「思う」が制約で、「われ」が制約されたものなのではないか。従って、「われ」と思うことそれ自体によって作られる 一つの綜合なのではないか。 ――『善悪の彼岸』54節
閃く (es blitzt)と言うのと同様、思う (es denkt)と言うべき であろう。コギト ということは、我 惟う(Ich denke)と訳するや過大となる。我 を仮定し要請するのは実用上の必要にすぎないのである。 ――エルンスト・マッハ『感覚の分析』(須藤吾之助、廣松渉訳)による
2020.5.12 tue.
何故にわれわれに何かしら関わりのある この世界が――虚構であってならないはずがあろうか。そしてその場合、「しかし虚構にはやはり創始者があるはずではないか」と問う者に対しては、――何故に ? とはっきり答えたらよかろう。この「あるはずだ」ということも恐らくは虚構に属するはずのものではなかろうか。 ――ニーチェ『善悪の彼岸』(木場深定訳)34
わたしの思い出は過去にさかのぼった。そうだ! こどものころ、遠い遠い昔に、盗人 ( ぬすびと )
2020.5.11 mon.
2020.5.10 sun.
宇宙に生命や人間が出現する確率は、事前にはほとんどゼロ。
2020.5.10 sun. ラクダの夢
ラクダの夢を見ようとしたら
2020.5.9 sat.
民俗学者になって12年かと気づいた
2020.5.8 fri. 他人の家
他人の家の前に人が集まっていた。
2020.5.8 fri.
上海の街路を短い葬列がやってくる。
老人 いつ?老人 なるほど。倒れてから五日間、とにかく生きてはいたというわけだな。老人 七十五年の生涯のうち四十年間を、牢獄に幽閉されて過した。最後の五日間は、とうとう自分の身体の中にとじ込められてしまった。パリ、イタリー大通り二十五番地。古い建物の六階の小部屋。ベッドで横になっていると、どこからか隙間風が吹き込んで来る。老人 墓碑銘は?老人 よし、行こう。行って、私にも墓に花をそなえさせてもらおう。老人 そう、終生の友……老人 私か? 私の名は、ルイ=オーギュスト・ブランキ。たったいま、上海に着いたところだ。
地球も、こうした天体の一つである。したがって全人類は、その生涯の一瞬ごとに永遠である。トーロー要塞の土牢の中で今私が書いていることを、同じテーブルに向かい、同じペンを持ち、同じ服を着て、今と全く同じ状況の中で、かつて私は書いたのであり、未来永劫書くであろう。 ──浜本正文訳『天体による永遠』